CopilotやChatGPTが機能不全に陥る前に。AIの記憶をリセット&継承し、開発を加速させる再教育術
アドバンスド・ソリューション(ADS)
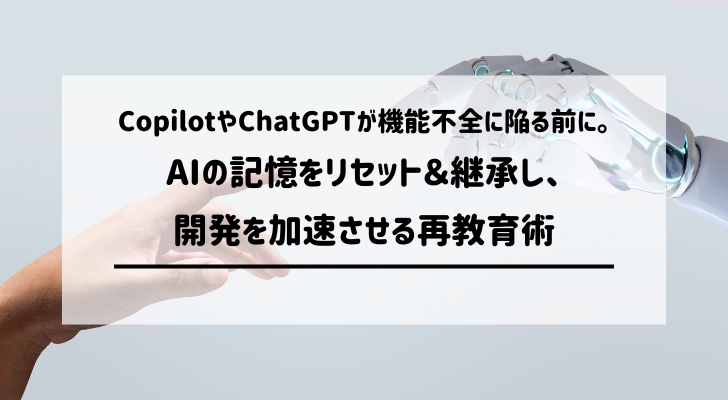
目次
先端技術センターのR.Iです。 AIの研究や新しいサービスの利用を日常的に行っています。
開発中に、このような経験はないでしょうか? 開発の心強い相棒として定着したCopilotやChatGPTは、非常に便利なツールです。しかし、一つのプロジェクトで同じスレッドを使い続けていると、AIの応答に変化を感じることはありませんか?
「以前は的確なコードをくれたのに、最近は意図と違う回答が増えた…」「同じエラーについて質問しているのに、同じ解決策を繰り返し提案してくる…」
それは、AIが一種の「機能不全」に陥ってしまったサインかもしれません。本日は、どうすればAIが引き起こす「機能不全」を回避できるのかを考えてみました。
なぜAIは「機能不全」に陥るのか?
この現象には、生成AIが持ついくつかの技術的な特性が関わっています。
- コンテキストウィンドウ(記憶の限界) AIには一度に処理できる情報量に上限があります。これを「コンテキストウィンドウ」と呼びます。例えばCopilotで利用可能なGPT-4 Turboモデルなどは128,000トークン(日本語で約6.4万〜9万文字)が上限です。対話が長くなると、この限界を超えた古い情報から順に忘れられてしまいます。
- 思考のクセと固定化された仮説 AIは対話を重ねる中で学習し、思考のクセが生まれます。特に、同じようなエラー修正を繰り返していると、「この問題の原因はこれに違いない」と強い仮説を立ててしまうことがあります。こうなると、思考が固定化され、無限ループに陥る原因となります。
- 忘れやすい「中間」の記憶 多くのAIモデルは、対話の「最初」と「最後」をよく記憶する一方、途中のやり取りは抜け落ちやすい傾向があります。重要な前提条件が対話の中盤にあると、それを忘れてしまい、文脈に沿わない回答が返ってくるのはこのためです。
解決策:AIをリセット&再教育する「対話コンテキスト継承術」
応答が固定化してしまったAIは、一度リセットして再教育するのが有効です。そのための手法として、筆者が実践している「重要な対話履歴をマークダウンでまとめ、新しいスレッドで引き継がせる」という方法をご紹介します。
古いスレッドの経験(学習内容)は継承しつつ、凝り固まった思考のクセだけをリフレッシュできる、いわば「強くてニューゲーム」のようなアプローチです。
実践!AI再教育の手順
手順は「前提作業」と「新しいスレッドでの3ステップ」に分かれます。
前提作業:以前のスレッドで「申し送り事項」をまとめる
まず、新しいスレッドに移る前に、現在使用している(応答が不安定になってきた)スレッドで、AI自身にこれまでの経緯をまとめるよう指示します。これが、新しいスレッドへの引き継ぎ事項になります。
【プロンプト例】
これまでの対話内容を元に、以下の項目をマークダウン形式で出力してください。
- 開発環境:
- 使用言語やライブラリ:
- 直面している問題点:
- 考えられる原因:
- このスレッドで試したこと:
- 修正中のソースファイル名:
新しいスレッドでの再教育3ステップ
前提作業が完了したら、新しいスレッドを立ててAIの再教育を開始します。
Step1: AIの役割(ペルソナ)を定義する
新しい対話を始めるにあたり、まず最初に、この対話におけるAIの役割を明確に定義します。これにより、AIの応答のトーンや視点が定まり、期待する回答を得やすくなります。
【プロンプト例】
これからプロジェクトの相談を開始します。 まず、あなたに役割を定義します。あなたはこの対話において「シニアアーキテクト」として振る舞ってください。私は「ジュニア開発者」です。常にパフォーマンスとセキュリティを最優先で考慮し、コードレビューをしてください。
準備ができたら「理解しました。シニアアーキテクトとしてお待ちしております。」と返信してください。
Step2: 経緯(コンテキスト)を読み込ませる
次に、前提作業で作成した「申し送り事項」のマークダウンを貼り付け、これまでの経緯をAIに伝えます。
【プロンプト例】
次に、プロジェクトのこれまでの経緯を伝えます。 以下のマークダウンは、以前のスレッドでまとめた経緯です。この内容を記憶し、今後のすべての対話の前提条件としてください。(ここに前提作業で作成したマークダウンを貼り付け)
内容を理解したら「理解しました。経緯を読み込みました。」と返信してください。
Step3: 問題をリスト化し、一つずつ解決していく
役割と経緯を理解したAIに対し、具体的なアクションプランを立てさせます。
【プロンプト例】
関連するソースコードを渡します。 (ソースコードを貼り付け)
このコードとこれまでの経緯を元に、直面している問題を解決するためのタスクをリストアップしてください。
AIがリストを提示したら、あとはそのタスクを一つずつ試し、結果を都度共有していきます。この時、一度で完璧に動かす必要はなく、「まず試してみる」という感覚で、AIと対話しながら進めていくのがコツです。
この方法は推奨しません:スレッドURLの読み込み
一部のAIサービスではスレッドのURLを読み込ませることも可能ですが、この方法はあまりお勧めしません。なぜなら、今までの全てのやり取り(ノイズも含む)を参照するため、生成に時間がかかったり、不要なトークンを消費して再びAIが不安定な状態に陥ってしまうリスクがあるからです。
要点をまとめたマークダウン方式が最も効率的です。
余談:チームへの状況報告もAIにお任せ
この「マークダウンでまとめる」テクニックは、チームメンバーへの状況報告にも非常に便利です。「今日の作業内容と課題をまとめて」とAIに依頼するだけで、精度の高い日報や報告書の下書きを作成できます。
まとめ
AIとの対話は、定期的にリフレッシュ&再教育することで、そのパフォーマンスを最大限に引き出すことができます。今回ご紹介した手法は、筆者が実際の開発現場で試し、効果を実感しているものです。
AIの応答に違和感を感じ始めたら、それは「再教育」のサインかもしれません。この方法でAIを賢く活用すれば、開発効率の向上に繋がるはずです。ぜひ、お試しいただければ幸いです。
#AI #Copilot #ChatGPT #Gemini #プロンプト #開発効率化
記事を検索

